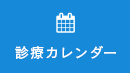噛み合わせが悪いとどうなる?放置のリスクと治療法を解説
こんにちは。渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」です。

噛み合わせが悪いまま放置すれば、顎関節症や肩こり、頭痛、消化不良など、全身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。見た目だけの問題ではなく、噛み合わせは日常生活や健康状態に深く関係しています。
体調不良の原因が、実は噛み合わせだったということも珍しくありません。
今回は、噛み合わせの重要性を見直すとともに、悪くなる原因、具体的な治療法までを解説します。
目次
正しい噛み合わせ

正しい噛み合わせとは、上下の歯が無理なく自然に噛み合い、食べる・話す・飲み込むといった基本的な機能を支える状態です。歯と歯が当たる位置・顎の動き・筋肉のバランスが取れており、力が均等に分散されていることが理想的な噛み合わせとされています。
口を閉じた時に前歯と奥歯が無理なく噛み合い、上下の歯列がスムーズに動くことが、正しい噛み合わせの基本条件です。この状態が保たれていれば、咀嚼や発音をスムーズに行えます。また、顎関節や筋肉への負担も最小限に抑えられます。
反対に、わずかなズレが長期間続けば、体に悪影響が生じるリスクが高まります。そのため、見た目だけではなく、普段から噛み合わせを意識しておくことが重要です。
噛み合わせが悪くなる原因

噛み合わせの乱れには、さまざまな要因が関係しています。ひとつひとつは小さな要因でも、積み重なることで大きな不調へとつながります。
噛み合わせが悪くなる主な原因は、以下の通りです。
成長期の歯列異常や生え変わりの影響
乳歯から永久歯への生え変わりの過程で、歯の並びが乱れると噛み合わせに影響が出やすくなります。永久歯が正しい位置に生えない、または重なり合って生えると、歯列全体のバランスが崩れます。
また、顎の成長が追いつかない場合も前後左右にズレが生じ、結果として噛み合わせが乱れる原因になります。
親知らず抜歯後の放置
親知らずが斜めに生えてきたり、途中で止まって埋まっていたりすると、周囲の歯を押し出す形で歯列を乱すことがあります。とくに、下顎の親知らずはスペースが足りないことが多く、前方の歯を押し出して噛み合わせ全体を乱します。
また、虫歯や事故などで抜歯した後そのまま放置していると、隣接する歯が傾いたり、噛み合う歯が伸びてきたりして噛み合わせがズレてしまいます。抜歯後は放置するのではなく、義歯やブリッジ、インプラントなどで早期に対応することが重要です。
悪習慣や生活習慣の積み重ね
噛み合わせに悪影響を与える習慣には、頬杖をつく、片側だけで咀嚼する、うつぶせ寝、歯ぎしり、食いしばりなどがあります。こうした悪習慣を日常的に続けていると、顎や筋肉のバランスが崩れていき、噛み合わせが乱れます。
とくに歯ぎしりや食いしばりは、寝ている間に無意識に行われるため、自覚がなくても歯や関節に強い負担を与えています。生活習慣の見直しは、噛み合わせ改善において不可欠です。
また、小さなお子さまの場合、指しゃぶりや口呼吸などの癖も、顎の発達や歯の生え方に影響を与えるため、保護者の早期介入が望まれます。
噛み合わせが悪いことで起こるトラブル

噛み合わせが乱れることで起こる問題は全身に影響するため、知らず知らずのうちに体調不良の原因となっている場合もあります。以下のような症状がある場合、噛み合わせが乱れている可能性があるため、注意が必要です。
顎関節症
噛み合わせが悪いと、顎の関節に不自然な力が加わり続けることで顎関節症を発症するリスクが高まります。顎関節症の症状は、口を開けたときにカクッと音がしたり、口が開きにくくなったり、痛みを感じたりすることなどが挙げられます。
さらに症状が進行すると、食事や会話が困難になる場合もあるため、重症化する前に治療することを推奨します。
顔のゆがみ
噛み合わせが悪く、片方の歯だけで噛むクセなどが続くと、顔の筋肉や骨格にも左右差が生じます。そうすると、顔全体がゆがんでくることがあります。
頭痛・肩こり・腰痛などの全身症状
噛み合わせの悪さは、首や肩、背中、腰など全身の筋肉に負担をかけます。噛み合わせのズレによって頭部の位置が微妙に傾き、そのバランスを取ろうとして他の筋肉に緊張が生じるためです。
慢性的な頭痛や肩こり、腰痛などの症状が現れるようになりますが、噛み合わせが関係していることに気付くまで時間がかかるケースも少なくありません。とくに、姿勢と噛み合わせの両方が悪い場合、負担は倍増します。
こうした不調はマッサージやストレッチなどでは根本の改善にはならないため、噛み合わせのバランスを整える必要があります。
歯の損傷、消化不良のリスク増加
噛み合わせが悪いと一部の歯に過剰な力がかかり、歯が割れたり、すり減ったりする可能性が高まります。特定の歯だけが頻繁に接触すると、その歯が摩耗して知覚過敏や痛みの原因になることもあります。
また、噛み合わせが悪いと噛みきれないことで咀嚼が不十分になりやすく、消化不良を起こしやすくなります。
噛み合わせの治療法

噛み合わせの悪さは、原因や症状に応じてさまざまな治療方法があります。放置すればさまざまな不調の原因になるため、早期に歯科医師に相談して適切な治療を受けることが重要です。
ここでは、主な治療法を紹介しますが、自身の症状に合った治療を選びましょう。
矯正治療
矯正治療は、噛み合わせのズレを根本から改善する方法です。歯を少しずつ移動させ、上下の歯が自然に噛み合うように整えていきます。
ワイヤー矯正やマウスピース矯正などの方法があり、矯正装置が目立ちにくいタイプなどもあります。矯正治療は見た目を整えるだけでなく、咀嚼機能や発音の改善など、機能面にも大きな効果を期待できます。
補綴治療
歯の喪失や破折によって噛み合わせが乱れている場合は、補綴治療が有効です。補綴とは、失われた歯の機能を人工物で補う治療で、被せ物(クラウン)・ブリッジ・入れ歯・インプラントなどの方法があります。
これらを用いて噛み合わせの高さや歯列のバランスを再構築すれば、機能的な改善が期待できます。歯を失ったまま放置すれば、部分的な歯に過剰な力がかかってトラブルを引き起こすことがあるため、早めの対処が必要です。
スプリント療法
スプリント療法とは、歯ぎしりや食いしばりによる顎関節や歯への負担を軽減する目的で、就寝中にスプリントと呼ばれるマウスピース型の装置を装着する治療法です。顎関節症の初期段階や、噛み合わせのズレが筋肉の緊張によって引き起こされている場合に有効とされます。
スプリントは歯列に合わせて個別に作られるため、咬合位置を安定させることで、無意識にかかる力が緩和されます。
ただし、並行して矯正や補綴などの処置が必要になることもあるので、歯科医師と相談しながら治療を進めましょう。
筋機能療法
噛み合わせの乱れには、日常の癖や筋肉の使い方も関わっています。筋機能療法は、舌・頬・顎などの口腔周囲筋のバランスを整えるトレーニングを行い、正しい舌の位置や飲み込みの動作を習得させる療法です。
とくに、筋肉が発達途中の子どもの矯正前後に用いられることが多く、歯並びの安定を助けます。
悪習慣・生活習慣の改善
頬杖、うつぶせ寝、片側噛み、姿勢の悪さなど、無意識の習慣が噛み合わせに影響を与えていることも多いです。そのため、噛み合わせを治すには、生活習慣の見直しが欠かせません。
筋肉・骨格・習慣の3つのバランスを取ることで、噛み合わせのズレの改善や予防につながります。
まとめ

噛み合わせの乱れは見た目だけでなく、身体全体のバランスや健康状態に影響を与える可能性があります。顎関節の不調、頭痛や肩こり、消化不良、歯の破損など、さまざまなトラブルの原因になり得るため、軽視すべきではありません。
さらに、噛み合わせの悪化は時間とともに進行し、放置すればするほど改善に時間を要します。自身の原因に合わせた矯正・補綴・マウスピース療法・生活習慣の見直しなどの方法により、噛み合わせの改善を目指しましょう。
噛み合わせの調整を検討されている方は、渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院は「一人ひとりに合った治療計画で歯を守ること」を意識して診療にあたっています。診療案内ページはこちら、ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。