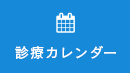喫煙と歯周病の深い関係!歯を守るために禁煙以外で大切なことも
こんにちは。渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」です。

喫煙は、肺や心臓に悪影響を及ぼすことでよく知られていますが、実は歯の健康とも深い関わりがあります。そのなかでも、歯周病との関係性が注目されており、喫煙が歯周病の進行を助長するという報告が数多く存在します。
この記事では、喫煙が歯周病に及ぼす具体的な影響や、禁煙によって得られる口腔内のメリット、さらに歯周病を予防するために禁煙以外で大切なことなどについて解説していきます。
目次
歯周病とは

歯周病とは、歯を支える骨や歯ぐきなどの組織が、細菌感染によって炎症を起こし、最終的には破壊されていく病気です。初期段階では歯ぐきの腫れや出血など軽い症状で進行し、痛みがほとんどないため気づかれにくいです。やがて進行すると、歯ぐきが下がって歯が長く見えるようになったり、歯を支えていた骨が溶けたりします。
初期段階では自覚症状が現れにくいため気づかれないことも少なくありませんが、最終的には歯が抜け落ちる恐れもある恐ろしい病気です。
歯周病の直接的な原因は、歯垢(プラーク)に含まれる細菌です。細菌が発生させる毒素によって歯茎に炎症が起こり、歯周病につながります。
歯周病は一度発症すると自然に治ることはありません。症状が進むほど治療も難航し、完治が難しくなるため、早期発見と予防が非常に重要です。
喫煙をすると歯周病になりやすいのはどうして?

歯周病の原因は歯垢に含まれる細菌だと説明しましたが、歯周病の発症には喫煙やストレス、偏った食生活といった、生活習慣や環境的要因も大きく関与しています。その中でも特に注目されているのが、喫煙です。
喫煙者は非喫煙者と比べて歯周病になりやすく、治療した場合でも効果が低くなりやすいとされています。では、どうして喫煙をすると歯周病を発症しやすくなるのでしょうか。
ここでは、喫煙すると歯周病になりやすくなる理由を解説します。
血流が悪化するから
長期間喫煙を続けていると、血管が収縮して血流が悪化します。血流が悪化すると、歯や歯ぐきに必要な栄養が運ばれず、歯周組織の細胞の活動が低下します。
そのため、歯周組織がダメージを受け止める力が落ち、歯周病になりやすくなるのです。また、炎症が起こったときに修復する能力も低下するため、歯茎の炎症が治りにくくなって歯周病が進行しやすくなります。
免疫力が低下するから
喫煙すると、口腔内や体全体の免疫力が低下します。そのため、細菌に対する抵抗力が弱くなり、歯肉炎や歯周炎などの感染症を発症しやすくなります。
唾液が減って口内が乾燥するから
喫煙者は、非喫煙者と比べて唾液の分泌量が少なくなるため、口内が乾燥しがちです。唾液には、口腔内の細菌を洗い流したり食べかすを除去したりする働きがあります。
唾液が減ってこれらの作用が不十分になると、汚れや細菌が長時間とどまりやすくなり、歯周病の進行を助長する要因となります。また、口腔内の乾燥は口臭の原因にもなります。喫煙は自分自身だけだけではなく、周囲にも影響を及ぼす可能性があるのです。
喫煙すると歯周病以外にもリスクがある?

喫煙は歯周病の進行に悪影響があることが明らかになっていますが、実はそれだけではありません。全身の健康にもさまざまな影響をもたらします。禁煙のモチベーションを高めるためには、歯周病以外のリスクを知っておくことも大切といえるのではないでしょうか。
ここでは、タバコによる歯周病以外の影響を紹介します。
口臭が強くなる
喫煙者の口臭は、周囲に不快感を与える大きな要因となります。タバコに含まれるニコチンやタールなどの成分が歯に付着すると、独特のにおいが発生します。
また、喫煙を続けていると唾液の分泌が抑制され、口の中が乾燥するため細菌が繁殖しやすくなります。これにより、タバコの臭いに加えて、雑菌の発生による口臭も強くなるのです。
タバコの臭いは歯磨きやうがいだけでは落としきれません。洗口液(マウスウォッシュ)を使用しても、一時的な改善にとどまることが多いです。口臭を改善するには、禁煙するのが望ましいです。
口内炎ができやすくなる
タバコに含まれる有害物質は口腔内の粘膜に刺激を与え、口内炎ができやすい環境をつくります。例えば、ニコチンや他の有害物質は粘膜の再生を妨げ、炎症の治癒を遅らせます。
そのため、口内炎やカンジダ感染などが慢性的に悪化しやすくなるのです。また、免疫力を低下させることによって、口内炎が完治しにくい環境も作り出します。口内炎が頻繁にできる方や治りにくい方は、喫煙の影響も一因として考えてみることが大切です。
がんになるリスクが高くなる
タバコは、さまざまながんの発症と深く関係しています。これは、タバコに含まれるタールやニコチンなどの化学物質が粘膜に取り込まれ、細胞を損傷させるためです。特に代表的なのが、口腔がん、喉頭がん、肺がん、食道がんなどです。
近年では、これらのがんの治療の一環として禁煙を勧められることも多く、がんリスクを下げるためにも、禁煙は重要な選択肢となります。全身の健康を守るためにも、禁煙することが大切なのです。
早産や低体重児出産のリスクが高まる
喫煙は妊娠中の女性にとってもリスクがあります。タバコに含まれる有害物質が胎盤を通過し、胎児の発育に悪影響を及ぼすためです。妊娠中に喫煙をすると、早産や低体重児出産のリスクが高まることが知られています。
喫煙によって血管が収縮して血流が悪化することで、胎児に必要な栄養が十分に供給されなくなるリスクもあります。妊娠前から喫煙を習慣にしている女性は、妊娠中は禁煙するよう意識しましょう。
歯周病を予防するために禁煙以外で大切なこと
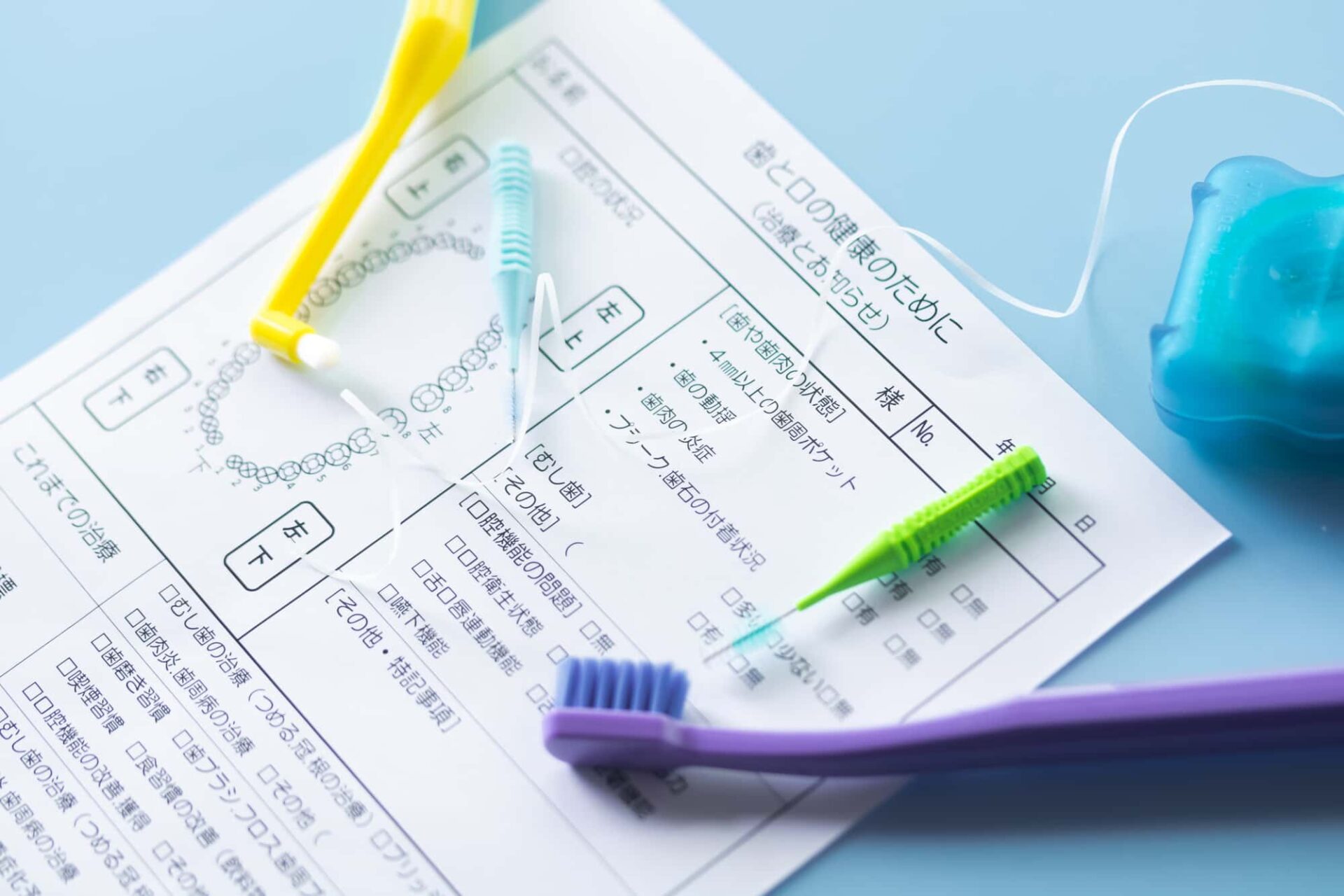
歯周病は、口腔内の衛生状態や生活習慣などの影響を大きく受ける病気です。以下に、禁煙以外で歯周病を予防するために大切なことについて詳しく解説します。
正しいブラッシングを身につける
歯周病の予防には、毎日の丁寧なブラッシングが不可欠です。歯周病の原因はプラークに含まれる細菌ですので、毎日丁寧に取り除くことが重要です。
歯周病を予防したい場合は、プラークが歯周ポケットの奥まで残らないように、歯ブラシを歯と歯茎の境目に45度の角度で当てて、小刻みに動かしましょう。力を入れすぎると毛先が広がり、有効にブラッシングできなくなるので注意してください。
1回の磨きにかける時間は最低でも3〜5分、1日3回を目安におこなうことが理想的です。軽く歯ブラシを当てて小刻みに動かすよう意識しましょう。
さらに、歯と歯の間には、デンタルフロスや歯間ブラシを使いましょう。デンタルフロスは1本の糸で、歯間にあるプラークを除去します。歯間ブラシは歯と歯の間が大きい場合に使用します。歯間には細菌が溜まりやすいため、毎日歯間のケアを行うことが大切です。
生活習慣を見直す
喫煙以外にも、歯周病のリスクを高める生活習慣はいくつかあります。例えば、間食の回数が多かったり、ダラダラと時間をかけて飲食したりする習慣は、口腔内の環境を悪化させやすくなります。
また、過度なストレスや睡眠不足も、歯ぐきの状態に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、睡眠中は唾液の分泌量が減少しがちで、細菌が繁殖しやすくなります。
これらの生活習慣を見直し、規則正しい生活を心がけることも、歯周病予防に欠かせません。
定期的に歯科検診を受ける
歯周病は初期段階では自覚症状が出にくく、痛みなどはほとんど感じられないため自分では気づきにくいです。そのため、歯周病を早期に発見・治療するには、定期的な歯科検診が欠かせません。
また、歯科衛生士による専門的なクリーニング(PMTC)を受けることで、日々のブラッシングで除去しきれない汚れやプラークも除去できます。すでに歯周病の治療を受けている方は、治療が終わった後も定期的に歯科医院を受診することが大切です。
まとめ

近年の研究によって、喫煙が歯周病の進行を早める大きな要因となることが明らかになってきています。喫煙によって血流が悪化し、免疫力が低下することで、歯周病菌の繁殖が促され歯周病になりやすい環境が整うのです。
そのため、歯周病を予防するためには、禁煙することが非常に重要です。
また、喫煙以外にも自然治癒の妨げになる生活習慣を続けていると、歯周病が進行することもあります。そのため、喫煙だけではなく、自分の生活習慣全般を見直して、歯周病のリスクを減らす努力をすることも大切といえます。
歯周病の治療を検討されている方は、渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院は「一人ひとりに合った治療計画で歯を守ること」を意識して診療にあたっています。診療案内ページはこちら、ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。