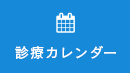子どもの歯並びが悪くなる原因は?今からできる予防法とは
こんにちは。渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」です。

子どもの歯並びは、見た目だけでなく噛む力や発音、将来の虫歯・歯周病リスクにも影響する大切な要素です。歯並びの乱れは幼少期の生活習慣や癖に起因することが多く、放置すると永久歯にも悪影響を及ぼす可能性があります。
歯並びの乱れは自然に改善することは少ないので、早い段階で原因に気づき、適切な対応を取る必要があります。
この記事では、子どもの歯並びが悪くなる主な原因と、日常生活の中でできる予防法について詳しく解説します。
矯正を検討したほうがよい子どもの歯並び

乳歯の段階から歯並びを注意深く観察することで、将来的な噛み合わせのトラブルを早期に見つけやすくなります。特に、以下のような特徴が見られる場合は、早めに小児矯正の相談を検討するとよいでしょう。
叢生
顎の大きさに対して歯が並ぶスペースが足りないと、歯が前後や左右にずれて凸凹に並ぶ叢生が生じます。歯みがきがしづらく、虫歯や歯肉炎のリスクが高まるだけでなく、舌の動きが制限されて発音が不明瞭になることもあります。
早い段階で顎の成長を促す装置を用いることで、永久歯がきれいに並ぶためのスペースを確保しやすくなります。
出っ歯
上顎の骨や前歯が前方に突き出していると、転倒時に歯を折りやすくなります。また、口が閉じにくくなって口呼吸が習慣化し、口腔内が乾燥することで虫歯や風邪を引きやすくなる傾向も見られます。
成長期にはヘッドギアや機能的矯正装置を使って、骨格のバランスを整える治療が効果的です。
反対咬合
いわゆる受け口と呼ばれる状態で、噛み合わせの不具合だけでなく、顔立ちにも影響が出る可能性があります。心理的なコンプレックスの要因にもなりやすいため、骨格の成長が活発な時期に下顎の前方成長を抑える治療を行うと、将来的な外科的処置を避けられる可能性が高まります。
交叉咬合
片側で噛む癖がつくと、顎の成長が左右で偏り、顔の左右差やゆがみにつながることがあります。成長期であれば、床矯正や拡大装置を用いて噛み合わせの位置を修正することで、短期間での改善が見込めます。
開咬
指しゃぶりや舌を前に出す癖(舌突出癖)が長く続くと、上下の前歯が接触せず、隙間ができる状態になります。食べ物をうまく噛み切れなかったり、発音が不明瞭になったりするため、習癖の改善とともに、マウスピース型装置や口腔筋機能訓練(MFT)を併用して治療を進めます。
子どもの歯並びが悪くなる主な原因

子どもの歯並びは、遺伝だけでなく、日々の生活習慣や身体の成長バランスの影響を受けます。特に乳歯の時期は、顎の発達や噛む力が永久歯の生え方に深く関わっており、癖や食生活の内容が歯並びに影響することも少なくありません。
ここでは、歯並びの乱れを引き起こす主な要因について解説します。
指しゃぶりや舌癖などの口腔習癖
長期間にわたる指しゃぶりや、舌を前に突き出す癖は、歯に継続的な力が加わることで歯の位置に影響を及ぼします。特に、前歯が前に押し出されたり、上下の前歯が閉じきらない開咬と呼ばれる噛み合わせの異常を引き起こしやすくなります。
また、舌の位置や動きが原因で発音が不明瞭になることもあるため、習慣が定着する前に早めに見直す必要があります。
口呼吸
常に口を開けて呼吸する習慣があると、口周りの筋肉がうまく働かず、上顎の発育が妨げられます。その結果、顎の幅が狭くなり、歯が重なって生える叢生のリスクが高まります。
アレルギー性鼻炎や扁桃腺肥大などが背景にあることもあるため、必要に応じて耳鼻咽喉科と連携して対処しましょう。
やわらかい食事の摂取
近年では柔らかい食事を摂っている子どもが多く、噛む回数が減少しているとされています。しっかりと咀嚼することは顎の発達に欠かせない要素であり、あごの骨が十分に育たないと、永久歯が正しい位置に生えるスペースが確保できなくなります。
成長期には、噛みごたえのある食材を積極的に取り入れることが大切です。
姿勢や寝方の偏り
頬杖をつく癖や、うつ伏せ寝が習慣化している場合も、歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。長時間、顔や顎に一方向から力が加わると骨の発育が偏り、噛み合わせがずれる原因となります。成長期の骨は柔らかく変形しやすいため、日常の姿勢にも注意を払いましょう。
子どもの歯並びが悪い状態を放置するリスク

子どもの歯列は、顎や筋肉、呼吸・発音機能と密接に関連しています。歯並びの乱れをそのままにしておくと、見た目の問題にとどまらず、全身の発育や将来的な健康面にも影響を及ぼすことがあります。
ここでは、歯並びの問題を放置した場合に生じる主なリスクについて解説します。
発音と咀嚼機能に悪影響を及ぼす
歯の位置がずれていたり重なっていたりすると、舌の動きが妨げられ、サ行やタ行など特定の発音が聞き取りにくくなることがあります。また、噛み合わせが悪いと食べ物をうまくすりつぶせず、丸呑みが増えて消化器官に負担がかかります。
咀嚼が十分に行われないと脳への刺激も減り、集中力や学習効率に影響を与えるという指摘もあります。
虫歯・歯周病のリスクが高まる
歯が凸凹に並んでいると、歯ブラシが届きにくい部分が増え、プラークがたまりやすくなります。清掃不良が続くと虫歯だけでなく歯肉炎のリスクも高まり、成長期に歯ぐきが腫れて出血しやすい状態が続くと、将来的に歯周病へとつながる可能性があります。
乳歯期の虫歯は永久歯の健康にも悪影響を及ぼすため、早めに対策を取ることが必要です。
顔のゆがみや全身の健康に影響する
噛み合わせの乱れをそのままにしていると、片側で噛む癖が定着し、顎の発達が左右で不均衡になることがあります。これにより顎や顔のゆがみが目立つようになり、肩こりや頭痛といった二次的な症状を引き起こすこともあります。
成長が落ち着いてから修正を試みる場合、外科的な治療が必要になることもあり、早期の対応が重要です。
心理的ストレスにつながる
歯並びの乱れは、子どもの笑顔や自己肯定感に影響を与えることがあります。人前で話すことに自信が持てず、友人関係や学校生活に消極的になるケースも見られます。
思春期は特に自己評価が揺らぎやすい時期であり、整った歯並びは前向きな表情や円滑な人間関係づくりにつながります。
将来的な治療負担が増える
子どものうちに歯並びの問題に適切に対処しなかった場合、大人になってから矯正を始める際に、抜歯や外科的処置が必要になるケースが増えます。治療期間も長くなり、費用や通院回数の面でも負担が大きくなるでしょう。
将来のコストや手間を抑えるためにも、成長期のうちに原因となる癖を改善し、必要に応じて早期に矯正治療を検討することが望ましいです。
子どもの歯並びが悪くなるのを予防する方法

乳歯から永久歯へと移行する時期は、顎の発育を促し、将来の歯並びを整えるうえで非常に大切です。この時期に適切な生活習慣を身につけることが、不正咬合の予防につながります。
以下に、子どもの歯並びが悪くなるのを予防する方法について解説します。
よく噛む習慣を身につける
柔らかい食事ばかりが続くと、顎に十分な刺激が加わらず、歯が並ぶためのスペースが十分に確保されないまま成長が終わる可能性があります。野菜をやや大きめに切ったり、根菜・海藻類など噛みごたえのある食材を取り入れることで、自然と咀嚼回数が増えます。
よく噛むことは唾液の分泌を促し、虫歯の予防にもつながります。
鼻呼吸を促し口呼吸を改善する
口呼吸の習慣があると、口元の筋肉がゆるみ、上顎の横幅がうまく広がらなくなる原因になります。鼻炎やアデノイド肥大がある場合は耳鼻咽喉科と連携し、根本的な原因を解消することが大切です。
自宅では口を閉じるトレーニングや、就寝時に口を閉じるテープを使うなど、鼻呼吸の習慣づけを意識して行いましょう。
指しゃぶり・舌突出などの癖を早めに見直す
指しゃぶりや舌を前に押し出す癖は、前歯の開きや出っ歯といった噛み合わせの乱れにつながることがあります。
しかし、乳幼児期は心の安定につながる行動でもあるため、無理にやめさせるのは避けましょう。絵本やごほうびカレンダーなどを活用して、段階的に卒業を目指すのが理想です。
必要に応じて、歯科医師や小児科医によるアドバイスや行動療法を取り入れるとより効果的です。
正しい姿勢と噛み合わせを意識する
頬杖やうつ伏せ寝といった姿勢の癖は、顎に片側から継続的な力がかかり、顔のゆがみや噛み合わせのずれを引き起こすことがあります。机や椅子の高さを体格に合わせて調整し、背筋が自然に伸びる環境を整えることで、顎への偏った負担を軽減できます。
枕の高さも重要で、首がまっすぐに保たれるものを選ぶようにしましょう。
定期検診を受ける
3ヶ月〜半年に一度の歯科検診では、歯列や顎の成長の状態を記録するため、わずかなズレにも早く気づくことができます。乳歯の段階で顎の広がりをサポートしたり、筋機能の訓練を始めたりすることで、将来的に抜歯を伴う矯正を回避できる可能性が高まります。
生活習慣についてのアドバイスも受けられるため、家庭での実践とあわせて継続することが大切です。
まとめ

子どもの歯並びは、遺伝だけでなく、日々の食事や呼吸、姿勢、生活習慣の影響を大きく受けています。歯列の乱れを放っておくと、見た目の問題だけでなく、噛む力や発音、虫歯や歯周病のリスク、さらには将来の矯正治療の負担にもつながる可能性があります。
成長期の今だからこそ、適切な習慣を整えることで、歯並びの安定を目指せます。お子さまの癖や変化を見逃さず、気になることがあれば早めに歯科医師へ相談しましょう。
お子さまの歯並びが気になっている方は、渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院は「一人ひとりに合った治療計画で歯を守ること」を意識して診療にあたっています。診療案内ページはこちら、ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。